スタッフ紹介
ご挨拶
障がいと共に暮らす人とその家族に
寄り添う歯科医療を目指します
歯科疾患の多くが生活習慣病のため、口腔ケアを中心とした生活習慣の改善は疾患の予防に寄与します。しかし、先天的、後天的障害は生活習慣の改善を困難にするため容易に疾患が悪化します。またいったん悪化すると、歯科疾患は自然治癒しないため、悪化の一途をたどり治療が非常に困難になり、治療にも精神的、身体的に著しい痛みを伴う事があります。
当センターでは、障害者歯科や歯科麻酔を専門とする歯科医師や歯科衛生士を中心として、障害の特性に配慮した歯科医療を目指しています。また日帰り全身麻酔や静脈内鎮静法などを応用して、精神的、身体的痛みを伴わない歯科治療を心掛けています。
皆様が歯科的健康を通じてより豊かな生活を営まれる事を職員一同祈念しております。
横浜市歯科保健医療センター 職員一同
スタッフ紹介
歯科医師
鈴木 將之すずき まさゆき
1978年(昭和53年)4月11日生まれ 牡羊座
【略歴】
| 2003年 | 鶴見大学歯学部 卒業、研修歯科医 |
| 2004年 | 鶴見大学歯学部 歯科麻酔学講座 入局 |
| 2014年 | 北水会記念病院 歯科・口腔外科 歯科麻酔 主任 |
| 2015年 | 鶴見大学歯学部 歯科麻酔学講座 助教 |
| 2021年 | 横浜市歯科保健医療センター 現職着任 |
【資格・所属】
| 日本歯科麻酔学会 専門医・認定医 |
| 日本障害者歯科学会 認定医 |
| 日本口腔顔面痛学会 認定医 |
| 日本抗加齢医学会 専門医 |
| アメリカ心臓協会(AHA)BLSインストラクター |
| アメリカ心臓協会(AHA)ACLSインストラクター |
| 日本救急医学 会員 |
| 日本歯科薬物療法学会 会員 |
| 日本有病者歯科医療学会 会員 |
| 日本歯科医学教育学会 会員 |
| 日本臨床麻酔学会 会員 |
| SCHEC NPO法人カンボジアの健康及び教育と地域を支援する会 理事 |

メッセージ
横浜市の地域医療に根差した診療を心がけます。診療は患者さんと私たちとの二人三脚です。なんでも相談しあいながら治療を進めていきたいと思います。
今野 歩こんの あゆみ
【略歴】
| 2009年 | 日本歯科大学新潟生命歯学部 卒業 |
| 2016年 | 昭和大学大学院歯学研究科 修了(歯学麻酔科学専攻) |
【資格・所属】
| 日本歯科麻酔学会 専門医・認定医 |
| 日本障害者歯科学会 認定医 |
| 日本摂食嚥下リハビリテーション学会 認定士 |

メッセージ
患者さんが安心して通院できるように、安全で快適な診療を心がけています。歯科のトレーニングで通われている子もたくさんいらっしゃいます。少しずつ慣れていきましょう。
篠木 麗しのき れい
【略歴】
| 2011年 | 明海大学歯学部 卒業 |
【資格・所属】
| 日本歯科麻酔学会 会員 |
| 日本障害者歯科学会 認定医 |
| アメリカ心臓協会(AHA)ACLSプロバイダー |

メッセージ
患者さん1人1人に寄り添い、安心・安全な医療を提供できるように努めます。
平沼 克洋ひらぬま かつひろ
【略歴】
| 2011年 | 大阪歯科大学歯学部 卒業 |
| 2016年 | 昭和大学大学院歯学研究科 修了 |
【資格・所属】
| 日本歯科麻酔学会 認定医・専門医 |
| 日本障害者歯科学会 会員 |

メッセージ
歯科治療に拒否の強い児童さんも多数来られますので、一人一人のニーズに合わせた診療を心掛けてまいります。
阿部 桂子あべ けいこ
【略歴】
| 2010年 | 東北大学歯学部 卒業 |
| 2025年 | 東京科学大学大学院医歯学総合研究科 修了 |
【資格・所属】
| 日本歯科麻酔学会 認定医 |
| 日本口腔外科学会 認定医 |
| 日本障害者歯科学会 会員 |

メッセージ
患者さんやご家族の方に「この病院に来て良かった」と言っていただけるよう、安心で安全な治療を心がけて参ります。個人のニーズに寄り添えるよう努めますので、ご相談ください。
池田 正一いけだ まさかず
【所属】
| 神奈川歯科大学客員教授 |
| 東京歯科大学臨床教授 |
| 医療法人鉄蕉会亀田総合病院歯科センター顧問 |
| 中野区歯科医師会障害者歯科指導医 |
| 神奈川県立こども医療センター歯科指導医 |
| 静岡市障害者歯科保健センター指導医 |

三浦 誠みうら まこと
【略歴】
| 1982年 | 日本歯科大学歯学部卒業 歯科麻酔学教室入局 |
| 1988年 | 日本歯科大学大学院修了 (生化学専攻) |
| 1988年 | 日本歯科大学歯学部付属病院一般歯科診療科 |
| 2001年 | 埼玉県歯科医師会口腔保健センター診療科長 |
| 2009年 | 横浜市歯科保健医療センター診療部長 |
| 2019年 | 横浜市歯科保健医療センター診療特任部長 |
【資格・所属】
| 日本歯科麻酔学会 認定医 |
| 日本障害者歯科学会 指導医・専門医・認定医 |
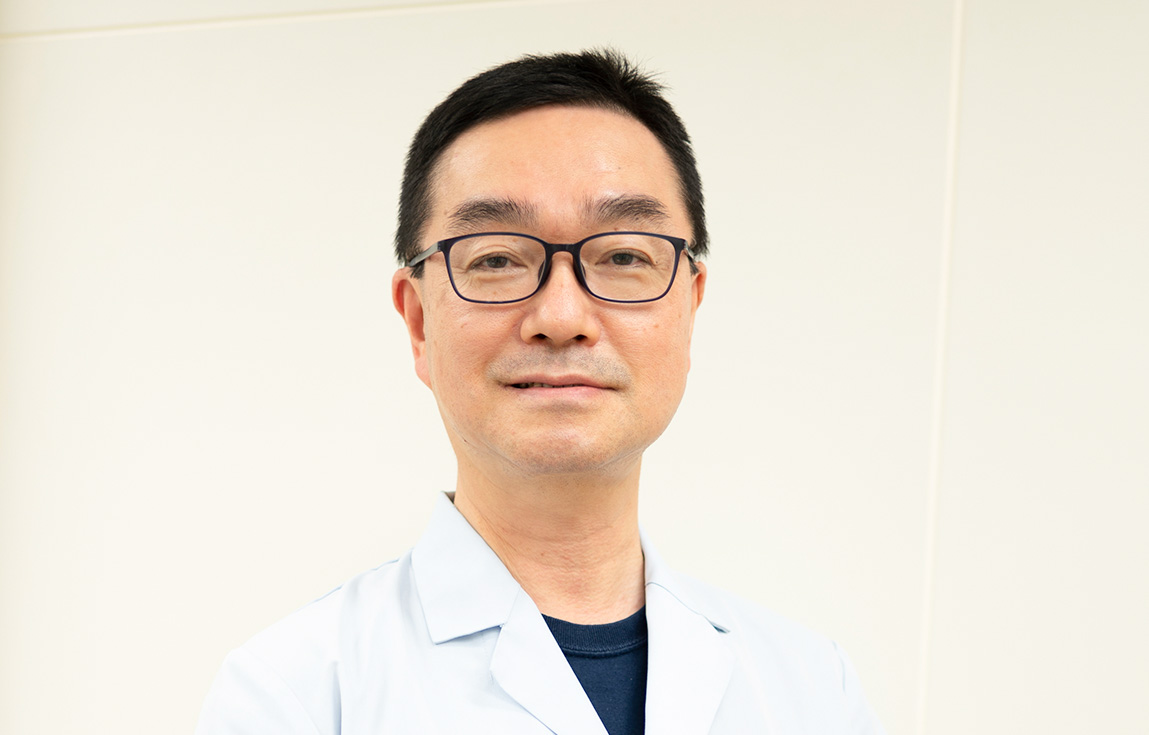
メッセージ
障がいと共に暮らす人とその家族に寄り添う歯科医療を目指します。
歯科衛生士
三輪 直子 みわ なおこ
【資格】
| 日本歯科衛生士会 認定歯科衛生士(障害者歯科) |
| 日本小児歯科学会 認定歯科衛生士 |
| 日本摂食・嚥下リハビリテーション学会 認定士 |
| 日本歯科麻酔学会 会員 |
| 介護支援専門員 |
メッセージ
安心して通っていただける診療を大切に、地域の皆さまのお口の健康を支えていきます。
歯科衛生士として、信頼していただけるケアや対応を心がけながら、専門的な知識を有したスタッフの育成にも取り組んでおります。
お困りのことがございましたら、お気軽にお声掛けください
川田 理絵 かわだ りえ
【資格】
| 日本歯科衛生士会 認定歯科衛生士(障害者歯科) |
| 日本歯科麻酔学会 認定歯科衛生士 |
メッセージ
患者さんとご家族、支援者の方々が笑顔で通院できる診療室を目指します。お口の中を通して一人一人に合う健康維持の方法を一緒に考えていきましょう。
藤田 千紘 ふじた ちひろ
【資格】
| 日本歯科麻酔学会 認定歯科衛生士 |
| 日本歯科衛生士会 認定歯科衛生士(障害者歯科) |
メッセージ
楽しく来院してもらえるよう患者さんの気持ちを大切にしています。
吉田 明日華 よしだ あすか
【資格】
| 日本歯科麻酔学会 会員 |
| 日本障害者歯科学会 会員 |
メッセージ
歯科に対する不安を無くし、お口の健康を維持するサポートができればと思います。
伊藤 優泉 いとう ゆい
【資格】
| 日本歯科麻酔学会 会員 |
| 日本障害者歯科学会 会員 |
メッセージ
笑顔と思いやりを大切に、心を込めて対応させていただきます。
管理栄養士
茂田井 圭菜もたい かな
【資格】
| 日本栄養士会 会員 |
| 栄養改善学会 会員 |
メッセージ
食に関する困りごとや悩みを一緒に解決し、ご家族皆さんが食事の時間が楽しい時となるように寄り添いたいと思います。

